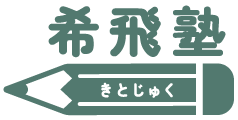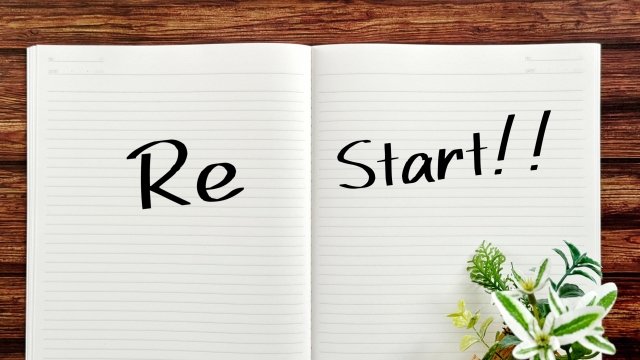社会科は日常の中にある。「覚えるだけ」→「つながる理解」へ!

「地名や年号は覚えているのに、テストになると点が伸びない・・・。」
「教科書を読んでも、なんとなく頭に入らないみたい・・・。」
「暗記が苦手で、社会は後回しになりがちです・・・。」
そんなふうに、社会科に対して、“なんとなく苦手”という印象を持つお子さんは少なくありません。保護者の方からも、「どうやって家庭でサポートすればいいのか分からない」というご相談をよくいただきます。
でも実は、社会科は家庭学習との相性がとても良い教科。ちょっとした工夫で、日常の中に“学びの種”を見つけることができるのです。
今回は、「家庭学習のサポート方法~社会編~」として、小中学生への具体的な取り組みも交えながら、社会科との向き合い方を一緒に見直していきたいと思います。
社会科は「つながり」と「実感」がカギ!
まず押さえておきたいのは、社会科は“暗記科目”ではなく“つながりの教科”だということ。地理・歴史・公民と分野は分かれていますが、すべてが「今の社会を理解するための知識」としてつながっています。
たとえば、小学生の地理では「北海道=酪農」「静岡=茶」と覚えるだけでなく、「なぜその地域でその産業が盛んなのか」を考えることで、記憶が定着しやすくなります。
中学生の歴史では、「鎌倉時代=武士の時代」と覚えるだけでなく、「その時代の人々の暮らしや価値観」を想像することで、理解が深まります。
社会科は、“実感”を持てると一気に面白くなる教科。家庭学習では、その実感を引き出す工夫がポイントです。
家庭でできる3つのサポートポイント:「話す」「見る」「つなげる」の3つの視点
①「話す」ことで記憶が定着する:社会科の知識は、声に出して話すことで定着しやすくなります。親子の会話の中で、「今日習ったこと」を話題にしてみましょう。おすすめの声かけとして、「今日はどんな地域のことを習ったの?」「歴史の授業で面白かったこと、教えて!」「選挙ってどういう仕組みだったっけ?」
話すことで、頭の中の情報が整理され、「覚えたつもり」が「使える知識」に変わります。
②「見る」ことで興味が広がる:社会科は、視覚的な情報と結びつけることで理解が深まります。地図、写真、映像などを活用して、教科書の内容を“リアル”に感じさせましょう。おすすめの取り組みとして、「地図帳を一緒に開いて、都道府県や地形を確認する。」「歴史ドラマやドキュメンタリーを一緒に見る。」「ニュース番組で、今の社会の動きを話題にする。」
見ることで、社会科が“自分ごと”になり、興味が広がります。
③「つなげる」ことで理解が深まる:社会科は、単元ごとに学ぶ内容が異なりますが、実はすべてがつながっています。たとえば、地理の「気候」と歴史の「農業の発展」は関係している。歴史の「戦争」と公民の「平和の仕組み」はつながっている。地域の産業は経済や政治の仕影響を与える。
これらのことを活かせるように、社会科のおすすめの家庭学習方法をご紹介します。
①「この出来事、今の社会とどう関係しているかな?」と問いかける。
②単元ごとに「前に習ったこととどうつながるか」を一緒に確認する。
③教科書の図や表を使って、仕組みを視覚的に整理する。
こうした“つながり”を意識できるようになると、より社会科の理解を深めていくことができます。
よくある小学生・中学生それぞれのつまずきポイントとしては、小学生では、「地名や用語は覚えているけど、実際の地域との結びつきが弱い」というケースが多く見られます。たとえば、「北海道=酪農」だけでなく、「なぜ酪農が盛んなのか」を考えることで、理解が深まります。
中学生では、「歴史の流れがつかめない」「公民のしくみが抽象的でわかりにくい」といった悩みが増えてきます。
「今と昔」、「自分と世界」をつなぐ科目が社会科です。子どもたちの「知る力」「考える力」「つながる力」を意識し、テストのためだけでなく、日常の中で「社会を見る目」を育てることが、結果的に得点アップにもつながります。
希飛塾では、保護者の方との連携も大切にしながら、一人ひとりの理解度に合わせて、学習を「楽しく」「深く」進めていきます。
体験授業や学習相談など、いつでも受け付けております。皆様からのご連絡をお待ちしております。