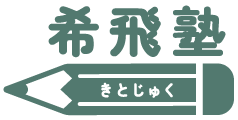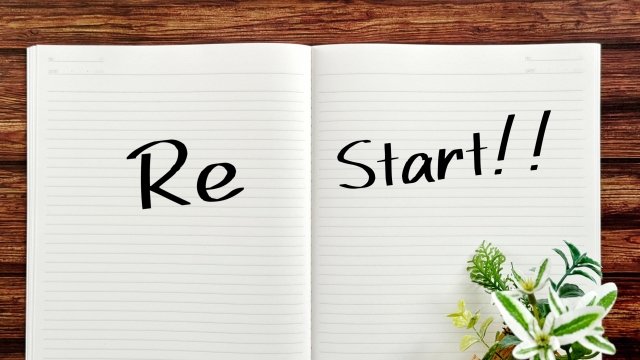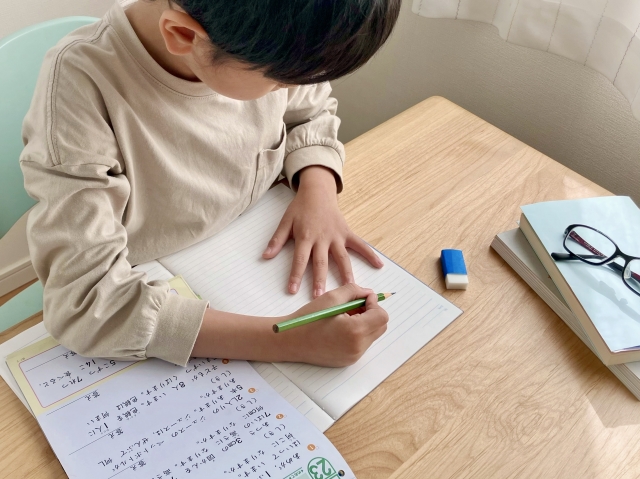数学が得意な生徒・苦手な生徒の特徴とサポート方法(中学生編)

中学生になると「数学が得意!」と胸を張る生徒と、「どうしても苦手…」と悩む生徒がはっきり分かれることが多くなります。保護者の方にとっては、「うちの子はどちらのタイプだろう?」「どう支えてあげればよいのだろう?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、数学が得意な生徒の傾向と苦手な生徒の特長、さらに具体的な対処方法についてお伝えします。
ここで、数学が得意な生徒に見られる、いくつかの共通点を挙げてみます。
・基礎計算が正確で速い:「基礎は大事」とよく言いますが、まさにその通りです。得意な子は四則計算や分数、小数、正負の数などの扱いに自信があり、問題を解くときに計算でつまずくことがありません。
・考え方を整理する習慣がある:ノートを見てみると、式や図、途中式が丁寧に書かれています。頭の中だけで考えるのではなく、「見える形」にする習慣があるのです。
・ミスの振り返りができる:間違えた問題に対して「なぜ間違えたのか」を確認し、次に生かせる子は、自然と実力を伸ばしています。
一方で、苦手な生徒にも特徴的なパターンがあります。
・計算のつまずきが放置されている:小学校内容や中1の計算でミスが多いまま、「分数嫌い」「符号が苦手」と放置されているケースです。応用問題以前に、基礎でストップしてしまいます。
・公式を「丸暗記」している:「二次方程式の解の公式」などを、意味を理解せず覚えるだけにとどまっていると、少しひねった問題に対応できません。
・途中式を書かず答えを急ぐ:計算過程を省略してしまうため、ケアレスミスが多発します。問題を見直そうとしても、自分がどこで間違えたのか分からないのです。
・「できない」という意識が強い:「数学はセンスがないから無理」と思い込み、最初からあきらめてしまう子もいます。心理的なハードルが、学習を妨げてしまうのです。
こうした得意、苦手の差を埋めるための対処法として、ぜひ、以下のことを意識してみてください。
・基礎力を徹底する:苦手な子には、まず計算練習の習慣化が第一歩です。毎日10分の計算ドリルを実施し、答え合わせ後は「どの計算で間違えたか」を赤で記録し、小さな成功体験を積み上げることで、「できる」という自信が芽生えます。
・途中式や考え方を書く習慣を身につける:途中式を丁寧に残すよう声がけしましょう。「どう考えたかを書いてみよう」と促していただくことが大切です。お子様が自分で整理する力を育てられます。
・間違いを“宝物”にする:得意な子はミスを分析しています。苦手な子にも「間違いは成長のチャンス」と伝えましょう。解き直しノートを作り、「次に同じミスをしない」仕組みをつくると効果的です。
・応用問題は「分けて考える」:文章題や図形問題は、一度に解こうとせず、問題文を区切って理解する練習が必要です。問題文に線を引き、「これは何を聞いているのか?」と確認し、図や表で整理して解いていくことが効果的です。
意外だと思われるかもしれませんが、中学生とはいえ、問題文が正確に読み取れていないことも多々あります。保護者の方が「問題文を一緒に声に出して読む」だけでも、理解が深まります。
・心理的サポートも大切に:「数学が苦手」と感じている子には、まず安心感が必要です。「頑張っているね。」「昨日より解けるようになったね。」など、結果より過程を評価してあげると、挑戦する意欲が湧いてきます。
保護者の方は「伴走者」です。勉強の環境を整えてあげること、習慣化を支えてあげること、成長を認めてあげること、これらのことがお子様が力を伸ばしていくうえで十分過ぎるほどのサポートになります。
内容的に難しく感じる部分は、それこそ塾や学校に任せましょう!
数学が得意な生徒は、基礎がしっかりしていて、考え方を整理し、間違いから学ぶ姿勢を持っています。苦手な生徒は、計算の基礎不足や暗記頼み、途中式の省略、そして「できない」という思い込みが壁になっていることが多いです。
基礎計算を毎日少しずつ、考え方を「書いて整理」する。間違いを振り返る習慣を意識し、問題を小さく分けて考える。結果ではなく努力を認める。
この積み重ねが、苦手意識を乗り越え、「数学は分かる!」という成功体験につながっていきます。
希飛塾では、こうした一人ひとりの特徴を踏まえながら、得意をさらに伸ばし、苦手を克服する指導を行っています。保護者の方と連携しながら、お子さまが安心して学びに取り組める環境づくりを大切にしています。