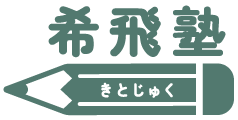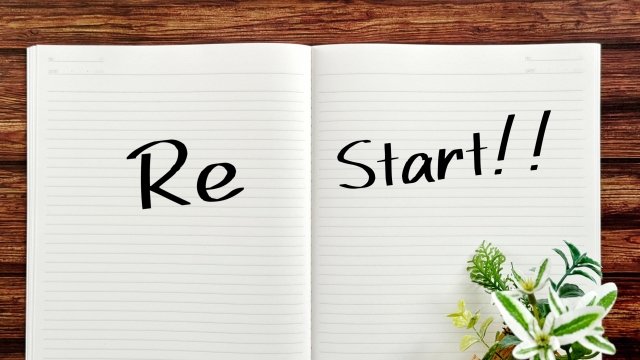科目別の得点アップポイント~社会編~

「地名や年号は覚えているのに、テストになると点が伸びない」
「教科書を読んでも、なんとなく頭に入らないみたい」
「暗記が苦手で、社会は後回しになりがちです」
保護者の方から、こういったご相談を受けることがあります。社会科は、小中学生にとって“覚えることが多い”という印象が強く、苦手意識を持ちやすい科目のひとつです。
しかし、社会は本来「身近なこと」と「歴史やしくみ」がつながる面白い教科。ちょっとした学び方の工夫で、得点アップはもちろん、興味や理解もぐっと深まります。
今回は、「社会科の得点アップポイント」を、具体的な練習方法や取り組み方とともにご紹介します。
社会科は「暗記」より「関係づけ」
まず押さえておきたいのは、社会科は単なる暗記科目ではないということ。もちろん地名や人物、出来事を覚えることは必要ですが、それ以上に重要なのは「どうつながっているか」「なぜそうなったのか」を理解することです。
たとえば、小学生の「日本の地理」では、都道府県名を覚えるだけでなく、「その地域で何が作られているか」「どんな地形があるか」といった情報を関連づけることで、記憶が定着しやすくなります。
中学生の「歴史」では、年号や出来事を覚えるだけでなく、「その背景にどんな社会の動きがあったか」「その後どう変化したか」を考えることで、記述問題にも強くなります。
得点アップのための3つのステップ
①「図・表・地図」を活用して視覚的に整理する
社会科は、情報量が多い分、視覚的に整理することで理解が深まります。
おすすめの家庭学習として、地図帳を使って地名や産業を確認する、年表を自作して、出来事の流れをつかむ、教科書の図や表をノートに写して、色分けする。
「見る→書く→話す」のサイクルを繰り返すことで、記憶が定着しやすくなります。
②「なぜ?」を考えることで思考力を育てる
社会科の得点力を左右するのは、「理由を考える力」です。
「どうしてこの地域では米づくりが盛んなの?」「この出来事の原因は何だったと思う?」と問いかけながら、子どもたち自身に考えさせる時間を確保したり、一緒に調べ学習に取り組むことが大切です。
ご家庭でできる取り組みとして、ニュースを見ながら「これは社会科で習ったことと関係あるね」と話題にしたり、歴史の出来事を「もし自分がその時代にいたらどうする?」と考えたり、「このグラフから何が読み取れる?」と問いかけてみたり。
「なぜ?」を考える力は、社会科だけでなく、他教科にもつながる思考力です。
③「問題演習」でアウトプット力を鍛える
最後に、実際の問題に取り組むことで、知識と理解を得点につなげる力を育てます。
単元で「よく出る問題」を整理し、繰り返し演習することで、出題パターンに慣れることが大切です
ご家庭では、教科書の章末問題を使って週1回確認テストをする、間違えた問題は「なぜ間違えたか」を一緒に振り返る、問題文を読んで、図や表を使って説明してみるのも良いと思います。
「解ける」だけでなく、「説明できる」ようになることで、記述問題にも強くなります。
小学生・中学生それぞれのつまずきポイント
小学生では、「地名や用語は覚えているけど、実際の地域との結びつきが弱い」というケースが多く見られます。たとえば、「北海道=酪農」だけでなく、「なぜ酪農が盛んなのか」を考えることで、理解が深まります。
中学生では、「歴史の流れがつかめない」「公民のしくみが抽象的でわかりにくい」といった悩みが多くあります。普段の生活から、ニュースや新聞、インターネットの記事などを、少しでも良いので目を通すことが大切です。
社会科は、子どもたちの「知る力」「考える力」「つながる力」を育てる教科です。テストのためだけでなく、日常の中で「社会を見る目」を育てることが、結果的に得点アップにもつながります。
学習相談など、いつでもお受けしています。お子様の学習面などで気になることがございましたら、遠慮なく希飛塾までご連絡ください。
ぜひ一緒に新しい一歩を踏み出してみませんか。